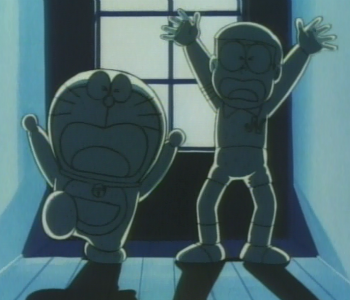|
生まれて初めて映画館に足を踏み入れた体験を、あなたは覚えているだろうか。
飲み屋でのトークネタとしても、オススメできるこの質問。僕にとっての初体験は、1984年『ドラえもん のび太の魔界大冒険』だった。数年前、友達に片っ端から同じ質問をぶつけてみたことがある。すると、「ドラえもん」が映画館初体験だという人の多いこと。ちなみに僕は1978年生まれ。劇場版ドラえもんは1980年から始まっているので、恐らく1975年くらい以降に生まれた世代は、映画ドラえもんジェネレーションと定義できるのかもしれない。もちろん、その後、猫型ロボットの好敵手はたくさん登場した。ちびまる子ちゃん、クレヨンしんちゃん、プリキュア、名探偵コナン、そして戦隊モノも多数。けれど、この春だって、稀代のヒットメーカー川村元気が脚本を手がけた『ドラえもん のび太の宝島』が封切られ、観客動員数は初登場1位を記録した。さらに、FM802のオフィシャルチャートOSAKAN HOT 100では、星野源が歌う主題歌が、こちらも1位を獲得。いかにドラえもんが根強い人気を誇るか、その地位が揺るぎないものであるかを証明した格好だ。
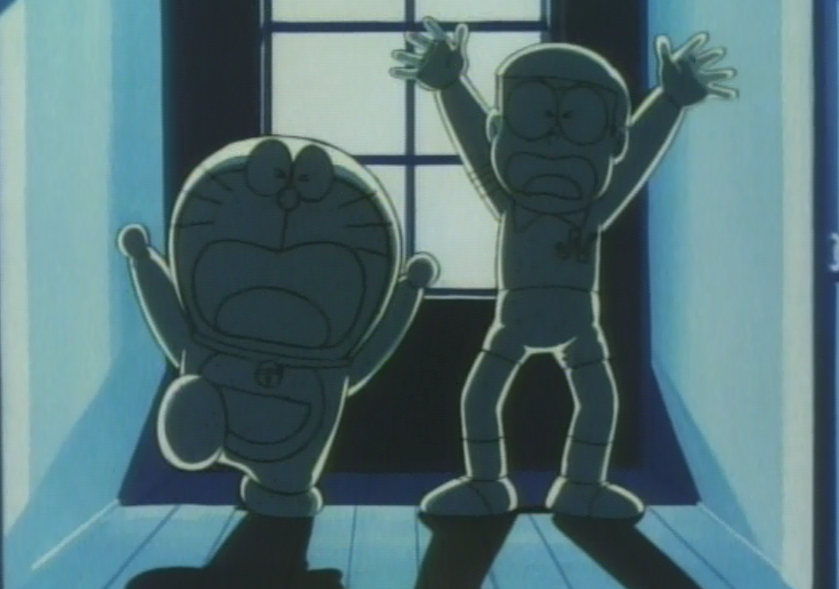 |
僕の初映画館は、ご多分に漏れず、おかあさんといっしょ。向かったのは、地元滋賀県大津市石山の東洋映画劇場、通称東劇だったと思う。「魔界大冒険」は、ドラミちゃんが初めて劇場版に登場した作品ということで、確か入口でドラミちゃんのグッズを何か貰ったような… 同時上映は、ハットリくんとパーマンがまさかの共演を果たすという珍作『超能力ウォーズ』。こんなにテンションの上がるスター揃いのラインナップだというのに、はっきり言って、映画についてはもう何も覚えていない。当時は入れ替え制ではなかったから、たぶん前の作品の途中から入ったのだろう。母に手を引かれてやっと歩けるほどに暗く、誰かがコーラでもこぼしていたのか、何だか床がにちゃにちゃしていて気持ち悪かった。何より、闇が怖いのなんので、「メジューサ」に見つめられたかのように、固まってしまった僕がいた。映画以上に、映画館に入ることがよっぽど「雅夫の魔界大冒険」だった。その東劇は翌85年の8月に閉館。今はもう跡形もない。
世の中がバブル景気に浮かれる前の80年代半ば、小学生の僕にとって唯一単独でアクセス可能な街だった石山にかつて3ヶ所あった映画館はすべて無くなり、取って代わるようにして、ニュータウンの最寄りのスーパーにはビデオの自動レンタル機が設置された。さらに、94年には市内で民間企業が運営する映画館が消滅し、なんと大津は唯一映画館のない県庁所在地という不名誉な称号を当時いただくことになってしまった。僕が映画館に向かうといえば、夏休みなどで出かけていた広島県福山市に限定されるという、なんとも切ない環境で思春期を迎えていたわけだ。
高校に入学して行動範囲が広がってきた僕は、大津のお隣、映画館が残っていた草津へと足を伸ばした。大人の階段を一段飛ばしで上る気だけは満々で、精一杯の背伸びをしていた僕は、もちろん母に手を引かれるのではなく、ガールフレンドの手を引いて出向いた。駅近くにあった草津シネマハウスは、1956年に開業していた老舗で、88年にはビルを建て増しして洋邦混映する3スクリーン体制のプチ・シネコン化していた頼もしい映画館。デートには時間の余裕が必要だとの理由で、開映よりもかなり早めに到着してチケットを(おそらくはカッコつけて彼女の分もおごりで)ゲット。作品は『ペリカン文書』。ジュリア・ロバーツとデンゼル・ワシントンが主演のサスペンス。映画雑誌『ロードショー』で仕入れた知識で必死に映画通ぶりながら、映画館の中で時間をつぶした。ただ、頭の中が完全に桃色で塗り込められていた当時の僕は、いかにして暗闇で彼女の手を握るか、なんなら腕を絡めるか、いや、あわよくば唇を重ねられるか、さらにそこで気分が高まった暁には… そんな妄想ではちきれんばかりとなっており、はっきり言って映画どころの騒ぎではない状態だった。だから、いざ上映が始まっても、ジュリア・ロバーツよりも彼女の横顔と胸の膨らみばかりをやぶにらみしていた。試しに『ペリカン文書』のWikipediaを閲覧してプロットをチェックしてみたが、はっきり言って何一つ覚えていなかった。ただ、読んでみたら面白そうなので、近いうちにちゃんと鑑賞してみようとは思う。
 |
前回の締めくくりに僕はこう書いた。
「映画体験というのは、時に作品そのものよりも、どこで(そして誰と)観たのかが大事なことがあって、逆に言えば、その場所を記録しておきさえすれば、記憶が芋づる式に蘇ることがあるからだ。次回以降、そうしてするすると引き出した記憶を具体的に披露しながら、ともすると失われゆきかねない映画館という装置の魅力について考えてみたい」
手始めに子どもの頃の地元映画館での鑑賞体験を脳内からするする引き出してみたところ、芋づる式に蘇ったのはそこで観た作品ではなく、映画館を冒険の場としていた記憶ばかりであった。決して褒められたものではないかもしれないが、こうした闇の恐怖やいかがわしい経験も映画館という装置の魅力だということを誰が否定できよう。
|
執筆:野村雅夫 FM802 DJ、京都ドーナッツクラブ代表。 1978年生まれ。ラジオDJ、翻訳家。大学では映画理論を専攻。FM802のレギュラー番組Ciao Amici!で行う3分間の新作映画評は看板コーナーとして名物化している。また、イタリア映画の配給や字幕制作も行い、毎年東京と大阪で行われているイタリア映画祭ではパンフレットで総論を寄稿。2015年は東京国際映画祭でナビゲーターを務めた。 |
 |